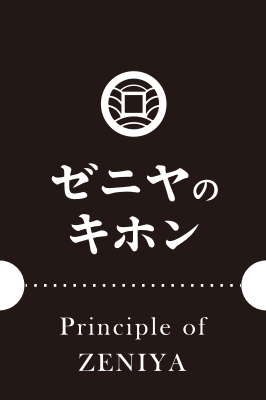《ゼニヤのキホン》 2025.4月号より
インドの寺院でホスピタリティについて考える
縁があってインドのチベット仏教寺院を訪れました。特別な式典と法要があってインド国内外から僧侶や支援者が集まってゲストはかなりの人数となりました。私が泊まったのは瞑想施設の一室でした。若い僧侶がお世話をしてくれるのですが、感心するのはその徹底したホスピタリティです。余談ですが地域のコミュニティとしての錢屋本舗本館のあり方を、人が集まれないコロナ禍に、心の距離を意識して見直すキッカケになったのが、このチベット人僧侶達からのメッセージでした。コミュニティにとって大切なのはソーシャルディスタンスとは無縁の心の距離であると感じたのです。それから「大切にしたい価値観」を発信し、共感の輪で繋がるコミュニティを意識するようになりました。
朝、まだ暗いうちに起きると程なく「お湯はいりますか?」と聞きに来てくれました。部屋の電灯がついたのを見ていたとしか思えません。部屋にはシャワーはありますが水しか出ないので頼むとバケツでお湯を持ってきてくれます。ビュッフェ形式の食事で汁物の鍋に手を伸ばすと、ボウルを持って鍋の横で待っていてくれます。そのボウルによそうとそのままテーブルまで運んでくれます。彼らはお年寄りを見かけると駆け寄って手を貸します。これはゲストに限らず老僧に対してもです。私の不注意でカーテンを壊してしまった時には恐縮する私に「これは元から木が腐っていたように見える」とわざわざ言ってくれ「急がなくていいから」と言っても15分もしないうちに修理してくれました。
当然ですが彼らは僧侶であってホテルマンではありませんからサービスを具体的に学んだわけではありません。なのに、なぜこんな振る舞いができるのか考えてみましたが、とにかく彼らはよく見ているのだと思います。そして相手が何を考え、どう思っているかを想像している、あるいは感じ取っているのだと思います。仏教の伝統に従い基本を学び、常に人に寄り添う準備ができている彼らにとっては、それも修行なのかも知れません。ここでは「私は(担当ではないので)わかりません」といったことがありません。全てその場で(何とかして)解決してくれます。
彼らは、お釈迦様の時代からの伝統を守るサンガ(共同体)で小さい子供から老人までが共同生活をする僧院で育つので、その生活の中でこのように育ったと考えるのが自然です。具体的に(マニュアルで)学んでいないからこそできることなのだと思います。
何年か前、夜に外灯の下でお経を読む小僧さん(10歳くらい)に「なぜ、そんなに勉強するの?」と聞いたら「仏になるため」と言うので「仏になってどうするの?」と聞いたら「人を救う」と答えてくれました。インドに住むチベット人の彼らは中国の侵攻によって国を追われて亡命を余儀なくされた、いわば難民です。その彼らを支援する(救う)つもりでいた私は恥ずかしくなりました。彼らを見ていると僧侶とは出家という生き方であって職業ではないとつくづく思います。
本質は常に抽象的ですが、その大切さが理解できていれば、その為にどうすれば良いかといった具体的な行動は自らが決めればいいのです。作法を教えて心を学ぶという教育は日本にも元々あったはずです。マニュアルによる教育を見直さないと本当のホスピタリティは育たないと思いました。(文・正木)