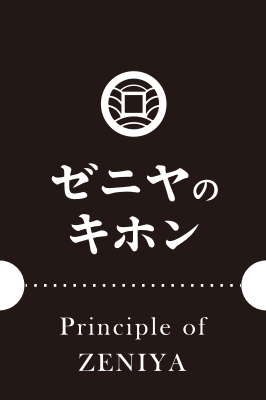《ゼニヤのキホン》 2025.3月号より
覗き見たり、盗み読んだりする経験
『錢屋ラリー亭』は、落語家の桂吉坊さんがゲストとのトークと落語で楽しませてくれるイベントです。「ラリー」という呼び名は錢屋本舗の施設を回ごとに場所を変えながら巡っていくことに由来しますが、吉坊さんとゲストの絶え間ない掛け合いも「ラリー」と呼ぶのに相応しいものでした。第4回は錢屋ギャラリーで3部制で行われ、ゲストは寄席三味線の浅野美希さん、人形浄瑠璃文楽三味線方の鶴澤友之助さん、浪曲師真山隼人さんと曲師(浪曲の三味線弾き)の沢村さくらさんでした。三味線奏者の話しを伺う機会はあまりありません。それぞれの三味線の違いから、奏者になったきっかけ、修行中の苦労話、楽しさ、奏法の特徴などを短い演奏を交えながら話してくれました。芸達者な皆さんは話しも上手で、聞き上手な吉坊さんとの話のラリーで会場は盛り上がりました。普段は舞台袖で演奏する寄席三味線の浅野さんが客前に出られるのも新鮮な光景で、小綺麗な着物姿やその所作に改めて魅了された観客もいらっしゃったのではないでしょうか。普段は見られないものを覗き見るような感覚は楽しく、背景にあるものを知ることで鑑賞の味わいが増します。これからも趣向を凝らしながら続くと思いますので第5回にもぜひご注目ください。
錢屋ギャラリーでは『本の虫クラブ』というイベントも月イチで開催しています。その名の通り本につく虫のように本が好きな人が集まって好きな本を紹介し合うのですが、イイ感じのコミュニティになりつつあります。最近は電子書籍もありますが、本が本のカタチをしている事を大切だと思っています。装丁や背表紙、帯、栞といった要素は単なるデザインではなく本との関わり方そのものをカタチづくっています。私は子供が成長の過程で親の本棚から盗み読むような体験はあった方が良いと思っていますが、そのためにもカタチある本や背表紙は重要です。
小学校の高学年から高校生くらいの間、親の本棚にある本に興味を持ち、こっそりと手を伸ばすことがありました。親の知らないところで子は成長し、それを見て親は驚くこともあるでしょうが、それはむしろ自然なことです。昨今の若者(この場合は大学生から新卒社会人くらい)は素直で真面目、押し並べて優秀である一方で、どこか幼さが残っているようにも感じます。要因は様々でしょうが、背伸びして大人の世界を垣間見る機会が少なくなっているのかも知れません。電子書籍が親のスマホやタブレットに格納されていると、子供は「盗み読み」することができません。情報は巷に溢れアクセスも容易ですが、「親の本」には、その家ならではの価値観や歴史が詰まっていて子にとって特別な意味があると思います。
デジタル化を否定するつもりはありませんし、リテラシーの観点から管理しやすい仕組みが必要なことは理解しています。しかし、前段の「覗き見る」感覚や、この「盗み読む」といった体験は好奇心の発露であるだけでなく精神的な成長を促す大切な経験でもあります。本は未知なる世界の扉であり、それを開いて入り込む――この身体的な感覚を伴う体験は、情報の取得だけでなく、情緒の面で自分の世界を広げる大切な機会だと思います。(文・正木)