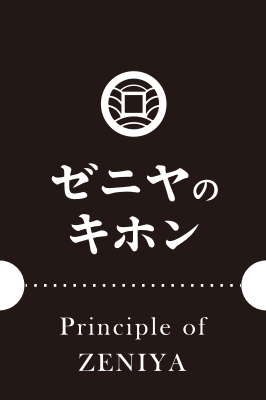《ゼニヤのキホン》 2025.5月号より
未来に行く
どこかに出かける準備をしていたので「どこに行くの?」と訊ねたら、嬉しそうに「未来に行く」と言われました。未来という言葉を知らなかった私は行くまでそれがどこかわかりませんでしたが、行った先は千里の万博会場でした。1970年、断片的な記憶しかありませんが私は5歳でした。「未来」は人が多くて凄いと興奮しました。私の目は出迎えてくれたロボットに釘付けになりました。未来から帰ってしばらく、兄はヤクルトや牛乳の空瓶で宇宙船を何隻も作っていましたし、私はロボットの設計図を何十枚も書きました。
70年万博のテーマは「人類の進歩と調和」でした。当時の日本は高度経済成長を果たし新幹線や超高層ビルといった最先端から、家電や自家用車の量産に至る技術大国としての発展をアピールしつつも、それが人類や社会全体と調和する必要があるという、冷戦や公害といった当時の社会的課題を反映したものでした。「戦後の終わり」を言いだしたのもこの頃からで戦後復興を遂げた日本が、平和と国際協力を重視する国家であることを世界に示す意味も持っていました。
成功裏に終わったとされるこの万博ですが「あれ以降、大阪が駄目になった」と評する方もいました。まだ30代で経営を学ぶために色んな勉強会に出ていた頃に「中央(政府と言う意味でしょう)の金と企画に頼って成功した体験で大阪が地方都市になり下がった」との視点で語られたその言葉は印象的で今でも覚えています。
今回の大阪・関西万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」がテーマです。この背景にある今の日本とは何でしょうか?発展を優先し環境破壊してきたのは、当時仲間入りした先進諸国で、今やその見直しは地球規模のテーマとなりました。国内ではかつて公害を生み出しましたが、大気汚染、排水処理・水質浄化、土壌汚染対策等の分野ではそれを克服しました。その段階で予測し地球環境にまで目を向けることができていたならば、日本は現在の脱炭素、マイクロプラスチック(リサイクル)、再生可能エネルギーといった地球規模の環境対策で世界をリードできたかも知れません。これは技術ではなく政治の問題だったでしょう。自らが先頭に立って当事者責任を発揮するリーダーシップがなければ、この地球規模の問題は誰も解決できないのでしょう。
また、ヴィジョンなき技術はユーザーを置き去りにした多機能家電の例に集約されます。使わない高機能に高額を支払う人はなく家電のシェアは奪われました。平和については日本がリードするゲーム技術の軍事転用は気になるテーマです。どんな未来をつくりたくて技術を活用するのでしょうか?結果として何を残すのでしょうか?明るく前向きで、それを実現する勤勉さを持ち合わせる日本人ですが、(あくまでも私見ですが)過去を総括して未来をつくることは苦手だと思います。過去の成功に倣いながらも、同じ失敗をしないように期待したいです。
岡本太郎が縄文土器から着想した太陽の塔は、千里の万博公園に今も残っています。テーマプロデューサーだった彼は内部に「生命の樹」を宿しました。「いのち輝く未来」で、得るものは技術革新によって変わるでしょうが、求める本質は変わらない気がします。その大切さを見つめる万博に期待します。(文・正木)