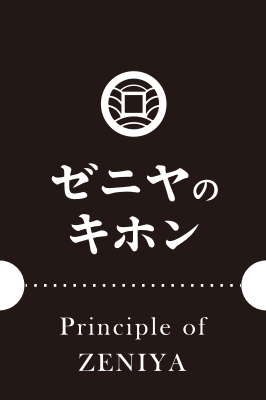《ゼニヤのキホン》 2025.2月号より
テーブルのようなアップルパイ
「例えて言うならこのテーブルのような…」と自分で話しながら可笑しくなりました。寒い時季に暖房の効いたカフェで、アイスクリーム添えの温かいアップルパイが提供できたら良いと思うのですが、どんなものならば錢屋カフヱーらしいのかを伝えたくて、会議の場で出た言葉です。試作で出されたのは薄くスライスされたリンゴが丁寧に重ねられた繊細で可憐なパイで味も良かったのですが、ダメ出しをしました。どう思ったか知りませんが、それでも若いスタッフは神妙に聞いてくれていました。
「らしさ」は、こう言うと大袈裟に思われるかも知れませんが意思と意識の賜物です。スタッフには、それほど大切なものであると知って欲しかったのです。ヒトであれモノであれコトであれ、一貫して積み重ねた時間(歴史)や、その背景にあるものに対する理解なしに「らしさ」は成立しません。と、まぁ、こだわりたい自分が勝手にこだわれば良いのですが、それを組織で共有するのは簡単ではありません。理屈でもなく、感覚だけでもない、曰く言い難いけれど確かに存在する何かだからです。
冒頭の「このテーブル」とは錢屋ギャラリーに置いてあるアルミ製の大きなテーブルのことです。私はその武骨さがカッコいいと思っています。イギリス製のそれは天板を打ち付けている木釘の頭は飛び出て揃わず、角は微妙に丸みを帯びています。無造作なディテールは、熟練の職人が「これでイイんだよ」と堂々と「らしさ」を主張しているように感じます。むしろこれ以上はやらないと決めた潔さが美しいのです。錢屋カフヱーに使われている分厚くエッジの効いたタイル、クリスマスツリーのプランターや練炭火鉢のカバーにも使われている黒皮(酸化被膜)鉄、ナポリタンのタマネギの切り方に至るまで例え話をしながら、これらのもつ共通の雰囲気を感じ取ってほしいと伝えました。「そんなアップルパイだ」と。
スマホで「アップルパイ」と検索すれば無数の素敵な写真と共にレシピまで出てきますが、答えはスマホの中にはなくココに(しかも、そのヒント)しかありません。近頃の若いモンを揶揄しているのではなく、私が若い頃でも「親より先生」「先生よりも憧れの人」「教科書より参考書」「学校より塾」「街ではなく自然の中に」、逆に地方出身者ならば「田舎ではなく都会に」「日本よりも外国」等と、身近にあるものよりも、少しでも遠くに価値高いものがあるのではないかという錯覚を、現実に向き合えずに持っていたように思います。これは多少なりとも誰しもが身に覚えのある感覚ではないでしょうか。若いスタッフには、社会に出てからの学びには正解はないので、自分たちで目の前にあるものから、あるいは自分の心の中から答えを見つけ出してもらいたいと思います。皆さんなら、どんなアップルパイを想像されますか?楽しみにしていてください。(文・正木)