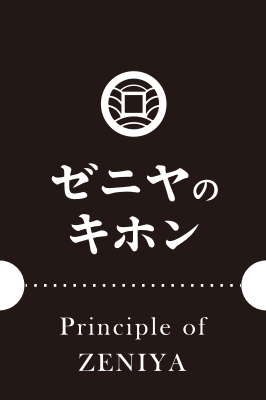《ゼニヤのキホン》 2025.1月号より
初収穫…失敗して想像した古代の日本
去年の2月から始めた「耕さない、肥料や農薬を用いない自然の営みに添った農業」ですが、11月に初めての収穫となりました。とは言っても、うるち米はほぼ全滅し古代米の赤米だけが育ってくれました。
うるち米はトヨサトという品種で、この地で自家採取されたものでしたから環境には合っていたはずですが、夏の暑さに加え、強風も吹きましたし、そもそも私が下手で水を十分に回せなかったこと、他にもモグラ、カメムシ、鹿、猪…様々な要因が考えられます。おそらく猪だと思うのですが、周りの稲をさんざん食べたすぐ横で、きっと寝ていたであろう腹立たしい窪みも2ヶ所ありました。初めてのことは失敗も楽しく、失敗からは学ぶことも多いので、それはそれで良かったと思います。そんな状況でも原種に近いとされる赤米(古代米)は育ってくれました。病害虫や過酷な環境に強いだけでなく、ノギ(殻の先の細いヒゲ)が長く、喉に刺さるので獣も食べないようです。実はこの赤米は籠神社(京都府宮津市)の御神米を種籾として分けて頂いたものです。籠神社は元伊勢神社とも言われ、天照大神と豊受大神が現在の伊勢の内宮と外宮に鎮座される前に4年間一緒に祀られた神社でもあります。第十代崇神天皇の御代とされていますから、神話・伝承の時代でもあり特定が難しいようですが歴史教科書的には古墳時代初期に当たります。両神が伊勢にお遷りの後に主祭神として祀られた彦火明命は養蚕や稲作の神様で毎年11月23日には「古代赤米新嘗祭」が斎行されます。
狩猟と採取によって比較的平等で安定した縄文の社会で、この力強く育つ赤米を栽培するようになって定住と備蓄が始まり、階層化され、より大きな社会が形成されました。その生き残った子孫が私たちなのだと想像します。鳥居の色にも象徴されるように日本では古くから赤い色には邪気を祓う力があると考えられていて、生命の糧としても重要であることもあり、神様に赤米を炊いて供える風習があったと考えられています。民俗学者の柳田國男は、赤飯の起源は赤米であると唱えています。遠い祖先に敬意を払い、来年は田圃の全面にこの赤米を植えるつもりです。品種改良されたうるち米とは違って雑穀のような米ですから味がどうというものではありませんが、古代から脈々と受け継がれた生命の糧を(邪気を払う縁起物のようなものとして)錢屋カフヱーで何らかの形でお召し上がり頂けるようになるかもしれません。(文・正木)